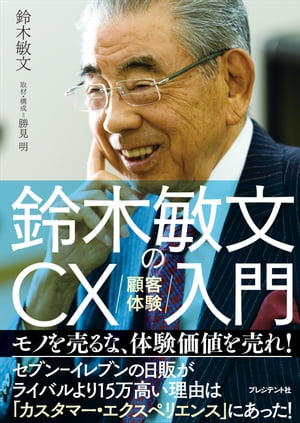
勝見明
(11)最新刊
鈴木敏文のCX(顧客体験)入門
(2022/05/31)【内容紹介】 日本ではDX(デジタル・トランスフォーメーション)の文字を見ない日はありませんが、ここ数年、もう一つ、「X」のつく用語として、「カスタマー・エクスペリエンス(Customer Experience、略してCX)」という概念が日本にも入ってきて、注目が集まっています。 CXは「顧客体験」もしくは「顧客体験価値」と訳されます。「商品・サービスの購入、利用における顧客としての体験」および「体験をとおして得られる感覚的・心理的価値」を意味するようです。 ヒト(お客様)は、モノをとおしてコトを体験することで価値を感じ、満足感を得る。モノの価値に対して、コトの価値とは、お客様が体験することで得られる価値、すなわち、顧客体験価値といえるでしょう。 カスタマー・エクスペリエンスの概念は二〇〇〇年代に入ってから注目されるようになったようですが、セブンーイレブンでは、一九七〇年代の創業当時から、仮説・検証を実践することで、お客様に満足していただける顧客体験を提供し続けてきたのです。 ★★★セブンーイレブン流・「これが欲しかった!」をつくり出す・真の【お客さま目線】とは? コンビニおにぎり、セブン銀行、100円コーヒー……。 数々のヒットを生み、日本の新しいライフスタイルをつくってきた鈴木敏文氏。 彼が約50年前からただ一人見抜いていた、潜在ニーズを拾いあげる「ストーリーづくり」の真髄は、創業以来セブンが徹底している「CX=カスタマー・エクスペリエンス(顧客体験)」にあった! ◎「お腹いっぱい」の人は何を食べるか ◎半分にカットした割高の大根が売れる理由 ◎おにぎりの販売は「新しい習慣」を生み出した ◎Francfrancには、なぜ、便座カバーが置いてないのか ◎動物園を「お客様の立場で」を見直して気づいた衝撃の事実 ◎花の売り手が花をもらって初めて問題点に気づく ◎横を見ずに目の前にいる顧客に目を向ける ◎「過去の延長線上」ではなく「未来の可能性」に目を向ける 「お客さまだけを見てください、ほかは見なくてけっこうです」 【目次抜粋】 イントロのようなまえがき モノ消費からコト消費の時代へ なぜ、セブンーイレブンの日販は他チェーンより一五万円も高いのか 「カスタマー・エクスペリエンス」とはコト消費 「仮説・検証」によりコト的な価値を提供する 「真冬の冷やし中華」が売れるわけ 第1章モノではなく、コト(体験価値)を売る時代へ 1 コロナ禍で顧客体験がより重要性を増した 到来する「消費縮小社会」 キーワードは「消費のレジャー化」&「家族ぐるみ」 コンビニも「脱・時間節約型消費」に対応する必要 売り手と買い手の関係は不可逆的に次のステージに向かう 2 メリハリ消費、ごほうび消費は典型的なCX型消費 現代の消費者に広がる「損したくない心理」 消費者が求めるのは「消費を正当化する理由」 3 同じものごとでも提示の仕方で売れ方が変わる 受けるのは「二〇%引き」より「現金下取りセール」 「真冬の冷やし中華」はなぜ売れるのか 4 CX重視で生まれたセブンーイレブンの実験店舗 セブンーイレブンの「ストア・イノベーション・プロジェクト」 「女子会」や「家飲み」に対応した売り場づくり 「ワイガヤ」で衆知を集めて売り場に活かす かつてないセブンーイレブンの誕生 5 なぜ、CX(顧客体験価値)が重要になってきたのか? 背景にあるのは消費の飽和 「お腹いっぱい」の人は何を食べるか 6 価格と価値の両にらみ 半分にカットした割高の大根が売れる理由 価値のないものはタダでもいらない 7 セブンプレミアムはなぜ、年間一兆四〇〇〇億円近くも売れるのか 常識を破った「上質感」と「製造者名の明記」 顧客体験価値の五つのタイプ 8 顧客体験価値を伝えるにはデザインも重要になる ユニクロ店舗のSENSE(感覚的経験価値) セブンーイレブンは「感覚的経験価値(SENSE)」をいかに高めたか 9 「売る力」とは顧客に満足してもらう体験価値を提供できる力 「あなたにとって、セブンーイレブンとは?」 10 セブンーイレブンは創業以来、顧客体験価値を提供してきた おにぎりの販売は「新しい習慣」を生み出した モノ売りで倒産したアメリカのセブンーイレブンとの違い 11 顧客体験価値にとって大切なのは売り手のフィロソフィ Francfrancには、なぜ、便座カバーが置いてないのか 「変わらない視点」と「新しいネタ」 第2章CX経営にはどんな発想法が必要なのか 1 常に顧客を起点に発想する 「お客様のために」ではなく「お客様の立場で」考える 2 顧客起点の発想はあらゆる分野で求められる 行動展示で顧客体験価値を提供して復活した旭山動物園 動物園を「お客様の立場で」を見直して気づいた衝撃の事実 3 「川モデル」ではなく、「井戸モデル」で考える 花の売り手が花をもらって初めて問題点に気づく 売り手の「まとめ売り」を買い手は「必要以上に買わされる」と感じる 誰もが売り手であると同時に買い手でもある 4 真の競争相手は「絶えず変化する顧客ニーズ」と位置づける 横を見ずに目の前にいる顧客に目を向ける 顧客体験価値は「絶対価値」の追求により実現する 5 顧客起点で新たな「事業連鎖」をつくっていく 「異業種間競争」の時代 顧客を起点にして既存の活動範囲や業界の境界を超えて発想する 6 経営の「動体視力」を鍛える おいしいもの」は「飽きるもの」でもある 7 「二匹目のドジョウ」をすくってはならない 脱・モノマネ思考 「他店見学をしてはならない」 CXとEXは両輪をなす 8 ブレイクスルー思考で未来を起点に発想する 「過去の延長線上」ではなく「未来の可能性」に目を向ける 未来の可能性は過去の論理では否定できない 高級食パンブームの草分けになった「金の食パン」 9 「成功の復讐」に縛られてはならない 過去の経験のフィルターがかかると変化が見えなくなる 未来創造は市場創造、顧客創造につながる 第3章顧客の求める体験価値をどのように生み出すのか 1 予定調和を壊す 「創造性とは、ものごとを結びつけることである」 「おやっ」を見つけるには「気づき」が大切 「ひまわりがブームになっているときには、たんぽぽの種をまこう」 2 「上質さ」×「手軽さ」の空白地帯を見つける 二律背反を両立させるトレードオフ戦略 市場の「空白地帯」には顧客の潜在的ニーズが埋まっている イベントで使うおしゃれな花を家庭用に 市場の「不毛地帯」に陥ってはならない 3 仮説力を鍛える1 〜疑問を発することが出発点 世の中でいわれていることを鵜呑みにせず、疑問を発する 仮説は「勉強」からは生まれない 4 仮説力を鍛える2 〜「先行情報」を見つける 情報を釣る「関心のフック」 情報は「一本釣り」より「はえ縄式」で収集する 5 仮説力を鍛える3 〜ミクロとマクロの両方の目をもつ 木を見て森を見、森を見て木を見る ミクロの直観力とマクロの構想力をもつ 6 仮説力を鍛える4 〜「川モデル」ではなく「井戸モデル」で考える 普通の生活感覚を大切にする 自分たちが商売の「主体になってはいけない」 7 仮説力を鍛える5 〜「素人の発想」を大切にする 素人の目線で素朴な疑問を解決すると新しい価値が生まれる 8 ものごとを「再定義」することで新しい価値を生み出す 定義は固定的なものではなく、一つだけとは限らない 第4章カスタマージャーニーに沿った戦略を考える 1 仮説を立てるとはカスタマージャーニーを想定すること 「顧客の通り道」をつくり出す 2 売り場という「舞台(ステージ)」で「物語」を生み出す 顧客体験価値の源泉は「物語性」にある 地域密着の個店主義が独自の「物語性」を生む ポストコロナ社会で重要性が増す個店主義 3 キュレーション戦略〜選択と絞り込みで新しい価値を生み出す キュレーションとは 駅ビルのルミネはキュレーションの成功例 キュレーションで重要なのは新たなコンセプトによる再定義 スーパーでも実行したキュレーション発想の品揃え 居心地のよい「セミラティス構造」の空間 4 演出力で「売る力」を高める 品の種類を絞り込むほど顧客は選択に迷わない 5 「高・中・低」の価格帯があると「中」が選ばれる 提示のされ方で選択肢が変わるフレーミング効果 顧客心理の「極端回避性」 6 CX時代には「お客様に近づく」ための「接客」が重要 「接客」こそが自己差別化の重要な要素になる 接客は「最後の一押し」 接客の基本は顧客への共感 人間は自分の考えに共感してもらえることがいちばんうれしい 7 オムニチャネル(ネットとリアルの融合)は流通の最終形 現代は「消費者による生活の合理化」の時代 自主マーチャンダイジングができる売り手が勝ち残る 8 データの向こうに新しい需要を発見する 販売データの奥にある買い手の心理を読む ビッグデータからは仮説は導き出せない 構成担当者によるあとがき 常に「お客様」を分母にして判断する
